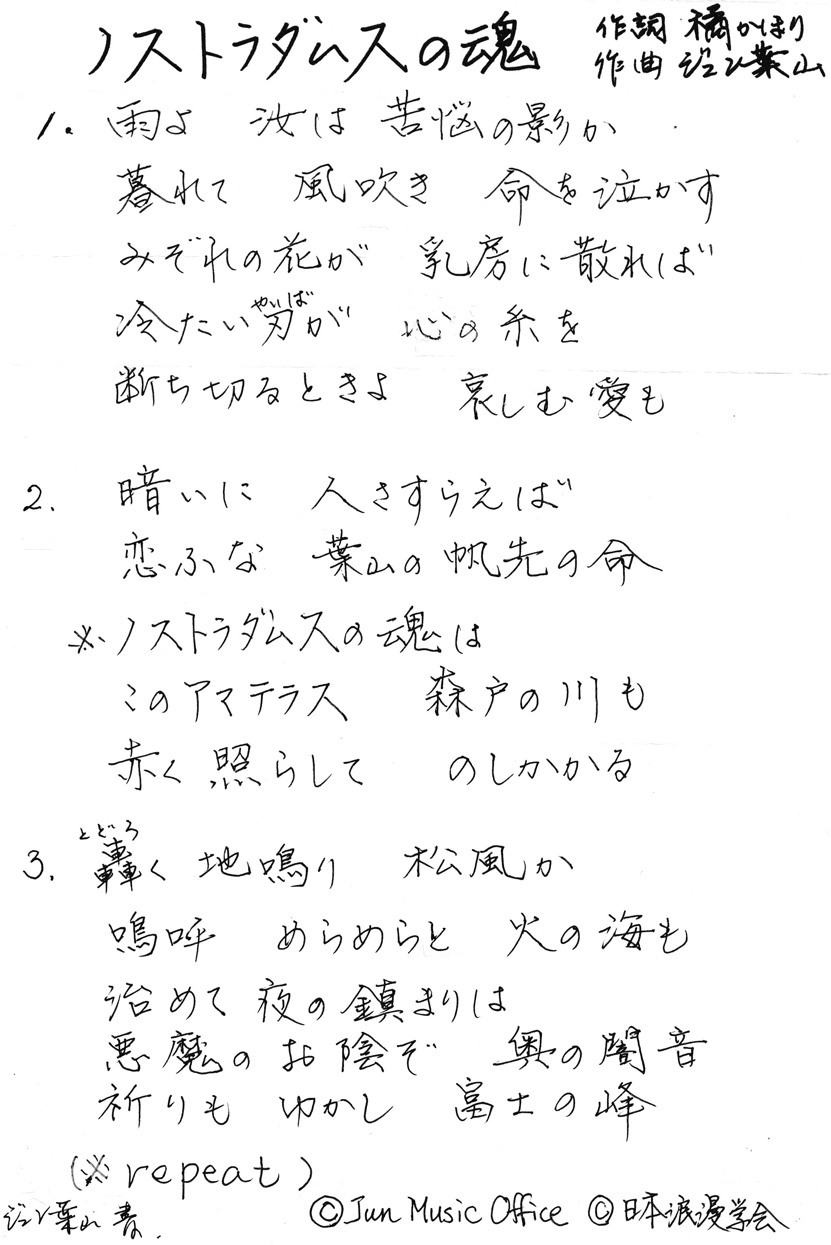作詞 橘かほり 作曲 ジュン葉山 2024.7.4
1.雨は降る降る 日暮れの浜辺
灯火ひとつ 濡れて泣く
あなたがくれた さくら貝
テラスに置くと すすり泣く
すがってくるの 私のむねに
2.岐れて二人 いつの日か
還ると言うの 耳もとで
そんなの嘘ね 吐息で判る
かわいい子たち 生きがいね
空っぽ貝が わたしなの
3.二度とないのね 激しい宵は
移ろい変わる 浜辺の砂丘
もとほり歩く なぎさ橋
もう来ないで 来ないで 来ないでいいの
濡れてさよなら なぎさ橋