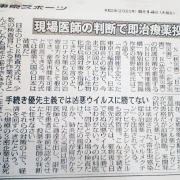日本浪漫歌壇 冬 如月 令和四年二月十九日収録
記録と論評 日本浪漫学会 河内裕二
歌会の行われた二月十九日頃から二十四節気では雨水となる。降る雪が雨へと変わり、積もった雪や張った氷が溶け始めることを意味している。雨水では時に春の気配を感じられる日も出てくるが、まだ寒い日が多く実感としては依然冬である。歌会当日も肌寒く夕刻には冷たい雨となり気温が下がった。半月ほど経てば二十四節気の中でもよく知られる啓蟄となる。その頃には春が近づいていることも実感できるだろう。
今回の三浦短歌会と日本浪漫学会の合同歌会は、二月十九日の午後一時半より三浦勤労市民センターで開催された。出席者は三浦短歌会から三宅尚道会長、加藤由良子、嶋田弘子、玉榮良江、新メンバーの羽床員子の五氏、日本浪漫学会から濱野成秋会長、岩間滿美子氏と河内裕二。三浦短歌会の嘉山光枝、清水和子の二氏と加藤さんのご友人の田所晴美氏も詠草を寄せられた。
寒風に凛と向かいて行く人に
吾も倣いて歩幅を正す 由良子
加藤由良子さんの作。ある日の早朝、とても寒いのに年輩の方が凜として歩くお姿をご覧になり、加藤さんもそれに倣って歩かれた。実際の体験を詠まれたそうで、お元気な加藤さんらしい内容の歌である。「歩く」という単純な言葉ではなく、「寒風に向かいて行く」や「歩幅を正す」のようなイメージの広がる表現を用いて臨場感を出されているところがお見事である。
記録と論評 日本浪漫学会 河内裕二
歌会の行われた二月十九日頃から二十四節気では雨水となる。降る雪が雨へと変わり、積もった雪や張った氷が溶け始めることを意味している。雨水では時に春の気配を感じられる日も出てくるが、まだ寒い日が多く実感としては依然冬である。歌会当日も肌寒く夕刻には冷たい雨となり気温が下がった。半月ほど経てば二十四節気の中でもよく知られる啓蟄となる。その頃には春が近づいていることも実感できるだろう。
今回の三浦短歌会と日本浪漫学会の合同歌会は、二月十九日の午後一時半より三浦勤労市民センターで開催された。出席者は三浦短歌会から三宅尚道会長、加藤由良子、嶋田弘子、玉榮良江、新メンバーの羽床員子の五氏、日本浪漫学会から濱野成秋会長、岩間滿美子氏と河内裕二。三浦短歌会の嘉山光枝、清水和子の二氏と加藤さんのご友人の田所晴美氏も詠草を寄せられた。
寒風に凛と向かいて行く人に
吾も倣いて歩幅を正す 由良子
加藤由良子さんの作。ある日の早朝、とても寒いのに年輩の方が凜として歩くお姿をご覧になり、加藤さんもそれに倣って歩かれた。実際の体験を詠まれたそうで、お元気な加藤さんらしい内容の歌である。「歩く」という単純な言葉ではなく、「寒風に向かいて行く」や「歩幅を正す」のようなイメージの広がる表現を用いて臨場感を出されているところがお見事である。
あと少し布団にもぐる寒い朝
時計見ながらあと少しだけ 光枝
作者は本日欠席の嘉山光枝さん。この歌の気持ちを理解できない人はいないだろう。「今の家は気密性や断熱性が高く昔の家のように隙間風が入ってくるようなこともないので、昔ほどはそう思わなくなったのでは」とは濱野会長。「あと少し」のリフレインがよいというのが皆さんのご意見であった。筆者などは、「あと少し」で二度寝してしまい「大惨事」となる恐怖を想像して背筋が寒くなった。
憶良よ遺言よ税よとめくるめき
昔の人もかくて逝くかや 成秋
作者は濱野成秋会長。山上憶良は遣唐使として最新の学問を修め帰国するも役人としては出世できず、昇進ではあるが伯耆や筑前の国守に任命され地方に飛ばされた。そこで詠まれた歌からは、その報われない気持ちが切々と伝わってきて、憶良が思っていたようなことを今ご自身が思っているのではないかという気がして、先人に向かって呼びかけられたとのこと。半分自虐的、諧謔的に書いたと仰ったが、まさに「貧窮問答歌」の現代版である。
「憶良」をルビのように「おくらら」と読むことについて質問があった。これはリズムを作るためで「憶良等」や「憶良ら」にしてしまえば「憶良のような」という違う意味になってしまうのでというご回答であった。「ら」を入れることで初句と二句のリズムが格段によくなるのは音読すれば明らかである。
時計見ながらあと少しだけ 光枝
作者は本日欠席の嘉山光枝さん。この歌の気持ちを理解できない人はいないだろう。「今の家は気密性や断熱性が高く昔の家のように隙間風が入ってくるようなこともないので、昔ほどはそう思わなくなったのでは」とは濱野会長。「あと少し」のリフレインがよいというのが皆さんのご意見であった。筆者などは、「あと少し」で二度寝してしまい「大惨事」となる恐怖を想像して背筋が寒くなった。
憶良よ遺言よ税よとめくるめき
昔の人もかくて逝くかや 成秋
作者は濱野成秋会長。山上憶良は遣唐使として最新の学問を修め帰国するも役人としては出世できず、昇進ではあるが伯耆や筑前の国守に任命され地方に飛ばされた。そこで詠まれた歌からは、その報われない気持ちが切々と伝わってきて、憶良が思っていたようなことを今ご自身が思っているのではないかという気がして、先人に向かって呼びかけられたとのこと。半分自虐的、諧謔的に書いたと仰ったが、まさに「貧窮問答歌」の現代版である。
「憶良」をルビのように「おくらら」と読むことについて質問があった。これはリズムを作るためで「憶良等」や「憶良ら」にしてしまえば「憶良のような」という違う意味になってしまうのでというご回答であった。「ら」を入れることで初句と二句のリズムが格段によくなるのは音読すれば明らかである。
厚い手で生くるを紡ぐラカンパネラ
フジコへミング御年九十 弘子
作者は嶋田弘子さん。昨年実際にフジコへミングのコンサートを観に行かれた。嶋田さんはその時のことをこう語られた。九十歳のフジコさんは舞台に杖をつきながら現れたが、ピアノを弾き始めると別人のようで、テレビなどで伝え聞いている彼女の波乱の人生を思いながら演奏を聴いていると涙が出るほどに感激した。力強くピアノを弾く分厚い手がとても印象に残った。
筆者はある新聞記事を読んだ。男性の漁師の方の話である。彼はテレビでフジコへミングがラカンパネラを演奏するのを観て深く感動し、自分も弾いてみたいと五十代でピアノを始める。楽譜も読めず楽器の経験もなかった彼が、この超難曲を何年も猛練習し、ついにフジコ本人の前で演奏したそうである。フジコのラカンパネラには人の心を動かす特別な何かがあるのだろう。「ラカンパネラ」はイタリア語で「鐘」を意味する。
春立てど凍てつく風の吹きたれば
天地つつまむ夢幻の衣に 裕二
筆者の作。春が来たのに冷たい風が吹いているので、夢や幻で世界を包んでしまおうというのが文字通りの意味である。とくに具体的なことは書いていないので、読者がそれぞれに解釈していただければよい。筆者は年が明けても暗いことが続く世の中を思って詠んだが、毎日寒い日が続いているから暖かい春の日を楽しく想像しているとしてもよいし、ファンタジックな世界を想像してもよい。
フジコへミング御年九十 弘子
作者は嶋田弘子さん。昨年実際にフジコへミングのコンサートを観に行かれた。嶋田さんはその時のことをこう語られた。九十歳のフジコさんは舞台に杖をつきながら現れたが、ピアノを弾き始めると別人のようで、テレビなどで伝え聞いている彼女の波乱の人生を思いながら演奏を聴いていると涙が出るほどに感激した。力強くピアノを弾く分厚い手がとても印象に残った。
筆者はある新聞記事を読んだ。男性の漁師の方の話である。彼はテレビでフジコへミングがラカンパネラを演奏するのを観て深く感動し、自分も弾いてみたいと五十代でピアノを始める。楽譜も読めず楽器の経験もなかった彼が、この超難曲を何年も猛練習し、ついにフジコ本人の前で演奏したそうである。フジコのラカンパネラには人の心を動かす特別な何かがあるのだろう。「ラカンパネラ」はイタリア語で「鐘」を意味する。
春立てど凍てつく風の吹きたれば
天地つつまむ夢幻の衣に 裕二
筆者の作。春が来たのに冷たい風が吹いているので、夢や幻で世界を包んでしまおうというのが文字通りの意味である。とくに具体的なことは書いていないので、読者がそれぞれに解釈していただければよい。筆者は年が明けても暗いことが続く世の中を思って詠んだが、毎日寒い日が続いているから暖かい春の日を楽しく想像しているとしてもよいし、ファンタジックな世界を想像してもよい。
百々伝ふ衣笠城の井の端に
佇み向かひて父祖の聲聴く 滿美子
作者は岩間滿美子さん。ご自身のルーツである三浦氏のご先祖を思って詠まれた歌である。初句の「百々伝ふ」は、謀反の罪を着せられ自害させられた大津皇子の辞世の歌からとのこと。
ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を
今日のみ見てや雲隠りなむ 大津皇子
「ももづたふ」は磐余にかかる枕詞である。岩間さんは衣笠城が長い歴史を持つことを表現したくてこの語を使ったそうである。「衣笠城の井」とは「不動井戸」と呼ばれる井戸で、言い伝えでは行基が杖で岩を打ち、水を湧かせたとされる。
池の鴨を見ながら自分は死んでゆくのだろうと思う大津皇子の「死」の歌に対して、城の井戸を見ながらこれからはご先祖のことを考えて生きてゆこうと決意する岩間さんの「生」の歌。どちらの歌も心に響く。
バイク音響かせて来る新聞に
立春の朝少し風あり 尚道
佇み向かひて父祖の聲聴く 滿美子
作者は岩間滿美子さん。ご自身のルーツである三浦氏のご先祖を思って詠まれた歌である。初句の「百々伝ふ」は、謀反の罪を着せられ自害させられた大津皇子の辞世の歌からとのこと。
ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を
今日のみ見てや雲隠りなむ 大津皇子
「ももづたふ」は磐余にかかる枕詞である。岩間さんは衣笠城が長い歴史を持つことを表現したくてこの語を使ったそうである。「衣笠城の井」とは「不動井戸」と呼ばれる井戸で、言い伝えでは行基が杖で岩を打ち、水を湧かせたとされる。
池の鴨を見ながら自分は死んでゆくのだろうと思う大津皇子の「死」の歌に対して、城の井戸を見ながらこれからはご先祖のことを考えて生きてゆこうと決意する岩間さんの「生」の歌。どちらの歌も心に響く。
バイク音響かせて来る新聞に
立春の朝少し風あり 尚道
三宅尚道さんの作。どこにでもある日常の光景だが、コロナ禍の現在、早朝に毎日きちんと新聞が届いたり、季節がいつものように移り変わったりという何でもないことがとても大切であると誰もが痛感している。バイクの音、新聞のインクの匂い、立春の朝の気温、吹いている風と、身体の感覚に訴える語が並んでいる。読むと感覚が刺激されるようで生きていることを再認識させられる歌である。
裏山の枇杷の花咲き近付きて
マスク外して香り吸い込む 良江
作者は玉榮良江さん。ご近所に枇杷の木があって花が咲くと散歩の際にその香りを楽しまれるとのこと。枇杷の花について『大辞林』には「初冬、枝頂に白色の小花を多数つける」とある。冬には咲く花も少ないので咲いていれば目を引くだろう。斎藤茂吉も枇杷の花の歌を詠んでいる。
枇杷の花冬木のなかににほへるを
この世のものと今こそは見め 茂吉
茂吉もやはり「香り」である。残念ながら筆者はその香りを知らないが、枇杷はバラ科なのできっとよい香りなのだろう。
初めてのビデオ通話に映りたる
老婆の我にギョッと驚く 員子
裏山の枇杷の花咲き近付きて
マスク外して香り吸い込む 良江
作者は玉榮良江さん。ご近所に枇杷の木があって花が咲くと散歩の際にその香りを楽しまれるとのこと。枇杷の花について『大辞林』には「初冬、枝頂に白色の小花を多数つける」とある。冬には咲く花も少ないので咲いていれば目を引くだろう。斎藤茂吉も枇杷の花の歌を詠んでいる。
枇杷の花冬木のなかににほへるを
この世のものと今こそは見め 茂吉
茂吉もやはり「香り」である。残念ながら筆者はその香りを知らないが、枇杷はバラ科なのできっとよい香りなのだろう。
初めてのビデオ通話に映りたる
老婆の我にギョッと驚く 員子
今回からご参加の羽床員子さんの歌。スマホを新しくしたのでビデオ通話をやってみたいと思って娘さんに頼んでやってもらうと、画面に映った自分の顔にびっくり。「わたし、いつもこんなにひどい顔しているの」と言うと「そうよ」と娘さんから間髪入れずに返ってきたと笑いながら仰る羽床さん。皆さん多かれ少なかれ同様の経験をされていて共感された。
テレビ電話のような昔はなかった新しいものを使い始めるということで、自分もまだ若いような気分になりワクワクしながら試みると自分の顔にギョッとする。そんな光景は何だか落語のようである。誰にとっても嫌な「老い」であるが、羽床さんの歌を読むと明るい気持ちになる。
雪山でふざけて買ったサングラス
手術のあとの眼覆へり 和子
作者は本日欠席の清水和子さん。白内障の手術をされたそうなので、歌のように昔購入されたサングラスを使われているのでしょうか。眩しいというのは、手術によって水晶体がクリアになったからで、ますます活動的でお元気になられた清水さんにお目にかかれるのが待ち遠しいです。
真の友どんな時にも頼もしく
アドバイスありやさしさもあり 晴美
テレビ電話のような昔はなかった新しいものを使い始めるということで、自分もまだ若いような気分になりワクワクしながら試みると自分の顔にギョッとする。そんな光景は何だか落語のようである。誰にとっても嫌な「老い」であるが、羽床さんの歌を読むと明るい気持ちになる。
雪山でふざけて買ったサングラス
手術のあとの眼覆へり 和子
作者は本日欠席の清水和子さん。白内障の手術をされたそうなので、歌のように昔購入されたサングラスを使われているのでしょうか。眩しいというのは、手術によって水晶体がクリアになったからで、ますます活動的でお元気になられた清水さんにお目にかかれるのが待ち遠しいです。
真の友どんな時にも頼もしく
アドバイスありやさしさもあり 晴美
田所晴美さんの作。おっしゃるとおりです。作者にはこの歌のような素晴らしいお友達がおられ、その方のことを思い浮かべて詠まれたのでしょう。ただ抽象的な語が多いために全体としてのメッセージが曖昧です。どんな時なのか、どのように頼もしいのか、どんなアドバイスなのか、どのようなやさしさなのか、どれか一つだけでもより具体的な表現があれば読者はイメージを膨らませやすいですが、もしかするとそこがポイントではなく「あなたには真の友がいますか」と問うているのかもしれません。
歌会終了後、濱野会長と岩間さんと共に衣笠仲通り商店街で開催されている企画展「三浦一族」に行った。三浦一族の歴史やゆかりの木像や場所などを説明するパネル展示であった。実物や実際の場所を訪れるのは、数も多くて時間がかかる。写真ではあるが、一度に見られるのはありがたい。展示も見やすく工夫されていた。
企画展は商店街の一角で行われていたため、会場まで商店街を歩いたが、昭和の香りのする本格的なアーケード商店街で、とても懐かしい気分になった。といっても、筆者の生まれ育った知多半島の小さな田舎町にはアーケード商店街などなく、このような立派なアーケード商店街となれば名古屋まで出ることになるので、決して身近だったわけではない。にもかかわらず懐かしく感じるのは、実際の商店街の記憶ではなく、こういうものが作られた昭和に自分も生きていたという記憶からであろう。いずれにせよ、昭和だろうが令和だろうが本日のような雨の日にはその本領を発揮する。展示にあった平安や鎌倉時代のものは間違いなく今後も残るが、昭和のものは果たしてどれだけ残るのだろうか。
歌会終了後、濱野会長と岩間さんと共に衣笠仲通り商店街で開催されている企画展「三浦一族」に行った。三浦一族の歴史やゆかりの木像や場所などを説明するパネル展示であった。実物や実際の場所を訪れるのは、数も多くて時間がかかる。写真ではあるが、一度に見られるのはありがたい。展示も見やすく工夫されていた。
企画展は商店街の一角で行われていたため、会場まで商店街を歩いたが、昭和の香りのする本格的なアーケード商店街で、とても懐かしい気分になった。といっても、筆者の生まれ育った知多半島の小さな田舎町にはアーケード商店街などなく、このような立派なアーケード商店街となれば名古屋まで出ることになるので、決して身近だったわけではない。にもかかわらず懐かしく感じるのは、実際の商店街の記憶ではなく、こういうものが作られた昭和に自分も生きていたという記憶からであろう。いずれにせよ、昭和だろうが令和だろうが本日のような雨の日にはその本領を発揮する。展示にあった平安や鎌倉時代のものは間違いなく今後も残るが、昭和のものは果たしてどれだけ残るのだろうか。