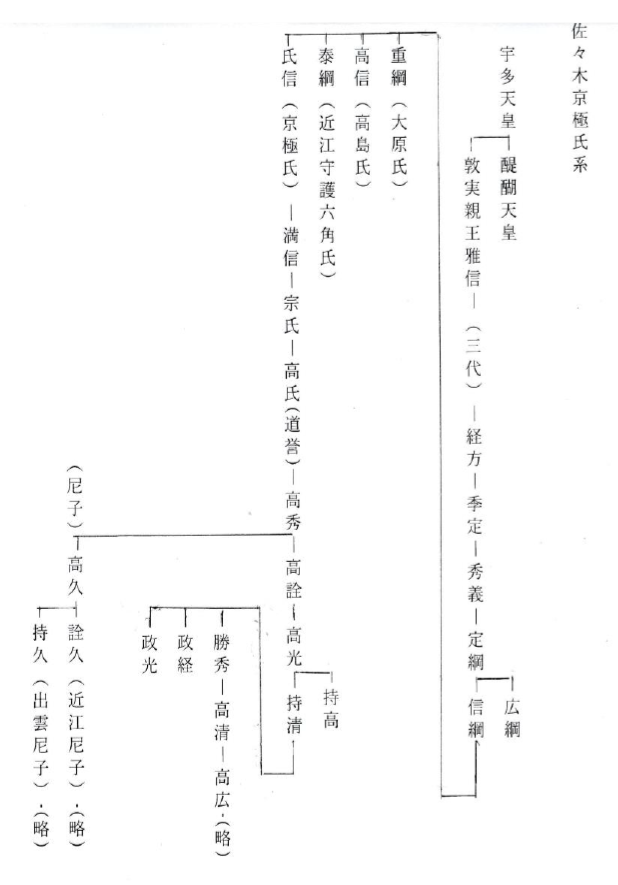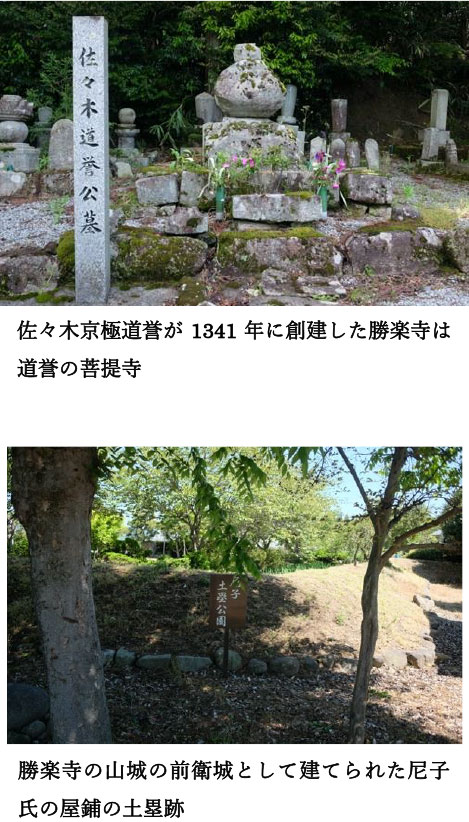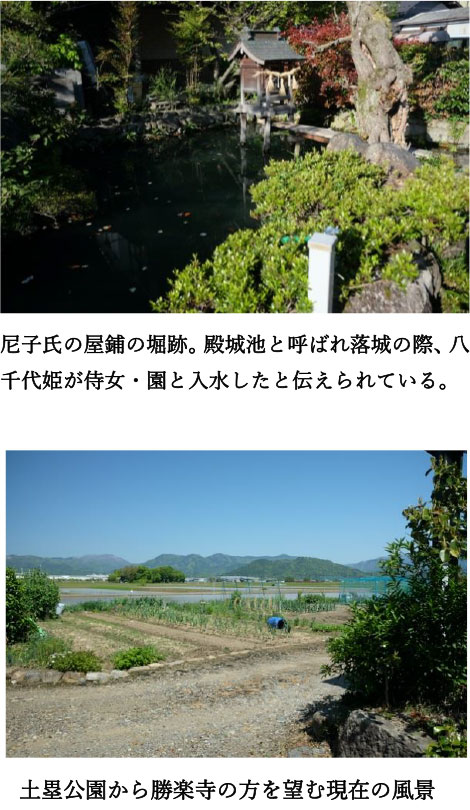古賀メロディと浪漫詩②
日本浪漫学会会長 濱野成秋
人生の並木路
一、泣くな妹よ 妹よ泣くな
泣けば幼い二人して
故郷を棄てた かいがない
歌詞も曲もまるで古賀さんが作ったような。だが作詩は佐藤惣之助である。
この兄妹の苦難の話は古賀さん、佐藤さんに通底する。いや、当時の貧農出身なら誰もが味わった故郷離脱劇である。
唱歌「ふるさと」は、「うさぎ追いしかの山」であり、日本人なら誰もが郷愁を歌う、のどかな歌だとしたがる。それは違う。現実はのどかどころか、碌に食えない故郷は如何に貧しく、抜け出したかった所か。これを詠んだ歌なのである。貧農で子沢山。次男三男は山の蔭の、陽の当たらない土地を耕し、年貢は高い。畔に畔豆を植え、二毛作で麦を植え、渋柿を干して甘柿にし、娘を紡績工場に息子を軍隊に。それでも食えない農家では、野兎や狸を追って棍棒で叩き殺して汁の具にして飢えをしのぐ。
「小鮒釣りしかの川」も、のんびりした歌ではない。泥臭い小鮒、どせう、フナ、ナマズ、ザリガニ、ヘビ、雀、何でも獲って食わねば生き延びられん。女工に出した娘は過労で肺病に。その妹は売られて女郎に。
「幼い二人して故郷を棄てた」兄と妹の境遇とはこんな有様だったのだ。
日本浪漫学会会長 濱野成秋
人生の並木路
一、泣くな妹よ 妹よ泣くな
泣けば幼い二人して
故郷を棄てた かいがない
歌詞も曲もまるで古賀さんが作ったような。だが作詩は佐藤惣之助である。
この兄妹の苦難の話は古賀さん、佐藤さんに通底する。いや、当時の貧農出身なら誰もが味わった故郷離脱劇である。
唱歌「ふるさと」は、「うさぎ追いしかの山」であり、日本人なら誰もが郷愁を歌う、のどかな歌だとしたがる。それは違う。現実はのどかどころか、碌に食えない故郷は如何に貧しく、抜け出したかった所か。これを詠んだ歌なのである。貧農で子沢山。次男三男は山の蔭の、陽の当たらない土地を耕し、年貢は高い。畔に畔豆を植え、二毛作で麦を植え、渋柿を干して甘柿にし、娘を紡績工場に息子を軍隊に。それでも食えない農家では、野兎や狸を追って棍棒で叩き殺して汁の具にして飢えをしのぐ。
「小鮒釣りしかの川」も、のんびりした歌ではない。泥臭い小鮒、どせう、フナ、ナマズ、ザリガニ、ヘビ、雀、何でも獲って食わねば生き延びられん。女工に出した娘は過労で肺病に。その妹は売られて女郎に。
「幼い二人して故郷を棄てた」兄と妹の境遇とはこんな有様だったのだ。
二、遠いさびしい 日暮れの路で
泣いて叱った 兄さんの
涙の声を 忘れたか
兄貴は法廷でも泣いて諫めるばかり。少年の頃が昨日のことのように思い出されるのである。
アメリカじゃ、こんな悲劇は通じない、日本政府は軍隊ばかりに力を入れた。なってないよ、日本の政治は。と、君は思うか? どうかな?
アメリカの経済学者ガルブレイスは1958年に『豊さの時代oと題する名著をだした。戦勝国アメリカの50年代はハリウッドに象徴されるアメリカニズム全盛の右傾化した時代で、ガルブレイスのいう「豊かな社会」(affluent society)という言葉はたちまち世界中を独り歩きをし、ジャパンも、おっつけ高度経済成長期に入ったので、アメリカ路線で当たり前の時代になった。
だがアメリカも移民難民で中西部から西へ。開拓時代は困窮続きの民衆が右往左往の有様。1920年代のジャズ時代でも、みな浮かれ騒ぎだと外見には喧伝していたが、ニューヨークのイーストサイドはロシア系、東欧系、ユダヤ系難民でごった返し、社会制度に金もかかる、飢えと病の底辺を日本人は全くしらない。白人でも貧しくて裸足で暮らす人々はそこら中にいて、poor whiteと呼ばれていた。こんなんじゃ母国に戻った方がましだと、当時の新聞の「身の上相談欄」出た記事は溢れるほどある。
それでも、農園の下働きで、暮らしを立てた日系移民の中にはしっかり貯蓄して、故郷に豪華な洋館を建て、村長の家より立派だと、見返した人も、沢山いた。だが、勤勉国家ジャパンは極貧だった。なぜ出遅れたか。なぜ軍備拡張ばかりに没頭したのか。
明治維新当時、富国強兵策が打ち出されたことは、日本人なら誰でも教科書で知っている。脅威はロシアだった。日清戦争で台湾や満州を手に入れ、「絶対国防圏」と称して頑張ったが、日露戦争で樺太の下半分の権益を得たものの、どれもこれも中途半端で、却って巨額の戦費を伴う日中戦争を継続する羽目に陥った。侵略と見做されて、アメリカからも見放された。
泣いて叱った 兄さんの
涙の声を 忘れたか
兄貴は法廷でも泣いて諫めるばかり。少年の頃が昨日のことのように思い出されるのである。
アメリカじゃ、こんな悲劇は通じない、日本政府は軍隊ばかりに力を入れた。なってないよ、日本の政治は。と、君は思うか? どうかな?
アメリカの経済学者ガルブレイスは1958年に『豊さの時代oと題する名著をだした。戦勝国アメリカの50年代はハリウッドに象徴されるアメリカニズム全盛の右傾化した時代で、ガルブレイスのいう「豊かな社会」(affluent society)という言葉はたちまち世界中を独り歩きをし、ジャパンも、おっつけ高度経済成長期に入ったので、アメリカ路線で当たり前の時代になった。
だがアメリカも移民難民で中西部から西へ。開拓時代は困窮続きの民衆が右往左往の有様。1920年代のジャズ時代でも、みな浮かれ騒ぎだと外見には喧伝していたが、ニューヨークのイーストサイドはロシア系、東欧系、ユダヤ系難民でごった返し、社会制度に金もかかる、飢えと病の底辺を日本人は全くしらない。白人でも貧しくて裸足で暮らす人々はそこら中にいて、poor whiteと呼ばれていた。こんなんじゃ母国に戻った方がましだと、当時の新聞の「身の上相談欄」出た記事は溢れるほどある。
それでも、農園の下働きで、暮らしを立てた日系移民の中にはしっかり貯蓄して、故郷に豪華な洋館を建て、村長の家より立派だと、見返した人も、沢山いた。だが、勤勉国家ジャパンは極貧だった。なぜ出遅れたか。なぜ軍備拡張ばかりに没頭したのか。
明治維新当時、富国強兵策が打ち出されたことは、日本人なら誰でも教科書で知っている。脅威はロシアだった。日清戦争で台湾や満州を手に入れ、「絶対国防圏」と称して頑張ったが、日露戦争で樺太の下半分の権益を得たものの、どれもこれも中途半端で、却って巨額の戦費を伴う日中戦争を継続する羽目に陥った。侵略と見做されて、アメリカからも見放された。
満州事変、日中戦争、ついには日米戦争へ。平民は一銭五厘の赤紙で戦地へ。軍隊では毎、貧農の日びんたびんたの連続だが、それでも水飲み百姓よりもましだと農家の次男、三男たちは入隊した。だから「欲しがりません、勝つまでは」の標語は言い得て妙で、この状況で、身売りをする妹を救うために志願したという。「人生の並木路」の兄と妹は召集令状を食らう前に、女郎女工に売られる前に、故郷を棄てて逃げたのである。この歌は1937年に発表されているが、真珠湾攻撃のたった四年前であり、貧困が人生を狂わせる仕組みがつい最近まであったのである。
三番と四番は一緒に出そう。トーンが違うよ。そこに気づいていただきたい。
三、雪も降れ降れ 夜道の果ても
やがて輝く 曙に
我が世の春は きっと来る
四、生きてゆこうよ 希望に燃えて
愛の口笛 高らかに
この人生の 並木路
この、三番、四番も含め、あの甘い声のディック・ミネさんの歌は絶妙で泣かせるけれど、一番、二番の後の、この内容では、打開策もなし、絶望感をこの程度の心がけで拭い去れるはずもない。
原節子が妹を演ずる映画のなかで唄われるわけだけれども、その後に作られた映画のストーリーを見ても、歌ほどの情念には欠けている。
歌詞の一番、二番が醸し出す切なさが映画やドラマの筋書きでは、興醒めだと思うのだが、皆さんは如何。むしろ、この歌だけを独立させて、筆者が指摘した個人の努力では如何ともし難い状況を噛みしめながら、日本の貧困とやるせない状況を噛みしめた方が、歌の心が、切々と峰に迫る。
三番と四番は一緒に出そう。トーンが違うよ。そこに気づいていただきたい。
三、雪も降れ降れ 夜道の果ても
やがて輝く 曙に
我が世の春は きっと来る
四、生きてゆこうよ 希望に燃えて
愛の口笛 高らかに
この人生の 並木路
この、三番、四番も含め、あの甘い声のディック・ミネさんの歌は絶妙で泣かせるけれど、一番、二番の後の、この内容では、打開策もなし、絶望感をこの程度の心がけで拭い去れるはずもない。
原節子が妹を演ずる映画のなかで唄われるわけだけれども、その後に作られた映画のストーリーを見ても、歌ほどの情念には欠けている。
歌詞の一番、二番が醸し出す切なさが映画やドラマの筋書きでは、興醒めだと思うのだが、皆さんは如何。むしろ、この歌だけを独立させて、筆者が指摘した個人の努力では如何ともし難い状況を噛みしめながら、日本の貧困とやるせない状況を噛みしめた方が、歌の心が、切々と峰に迫る。
佐藤惣之助も古賀政男も貧農の子で後に大成功者となるし、ガルブレイスもカナダの貧農に生れ、ハーバードからプリンストンへ加州大バークレーで気炎を吐く存在となったが、彼もアメリカ作家アンダーソンが描く『白人貧農』(Poor White)で、みなほぼ同時代なのである。
こうやって見ると、昭和7年、世界は大恐慌のさ中で、日本は日中戦争を始めたばかり。関東大震災からまだ十年と経たない時代。帝都の復興も充分でないのに、戦費が掛かる。国を挙げて軍備増強政策に躍起になっている。輸出相手国のアメリカとの関係が悪化して、西洋音楽などにうつつを抜かすより増産に汗を流せの時代である。強兵には税金がかかり、生産性は乏しいから、貧困層の救済などに国家としては手が回らない。
この歌を作詩作曲した古賀政男の二十歳代の暮らしも、どん底状態で、恋愛の懊悩を歌って生計を立てるなど、夢のまた夢。尋常な世界ではなかった。
古賀政男は明治大学に在学してマンドリン倶楽部を創設したとあるから、生活に困らない学生と思うなかれ。食事もままならぬ貧困状態で欠食に継ぐ欠食。マンドリンも売るしかないと思った矢先に、母親が5円何某を送ってくれた。もしマンドリンを売りに出していたら、今日の古賀メロディはなかったと、別の所で書いた覚えがあるが、佐藤惣之助も貧乏のどん底だった。
だから、古賀は佐藤の歌詞に涙しながら、この哀愁に満ちた詩に、切々と迫る名曲を与えたのだと筆者は思う。
こうやって見ると、昭和7年、世界は大恐慌のさ中で、日本は日中戦争を始めたばかり。関東大震災からまだ十年と経たない時代。帝都の復興も充分でないのに、戦費が掛かる。国を挙げて軍備増強政策に躍起になっている。輸出相手国のアメリカとの関係が悪化して、西洋音楽などにうつつを抜かすより増産に汗を流せの時代である。強兵には税金がかかり、生産性は乏しいから、貧困層の救済などに国家としては手が回らない。
この歌を作詩作曲した古賀政男の二十歳代の暮らしも、どん底状態で、恋愛の懊悩を歌って生計を立てるなど、夢のまた夢。尋常な世界ではなかった。
古賀政男は明治大学に在学してマンドリン倶楽部を創設したとあるから、生活に困らない学生と思うなかれ。食事もままならぬ貧困状態で欠食に継ぐ欠食。マンドリンも売るしかないと思った矢先に、母親が5円何某を送ってくれた。もしマンドリンを売りに出していたら、今日の古賀メロディはなかったと、別の所で書いた覚えがあるが、佐藤惣之助も貧乏のどん底だった。
だから、古賀は佐藤の歌詞に涙しながら、この哀愁に満ちた詩に、切々と迫る名曲を与えたのだと筆者は思う。