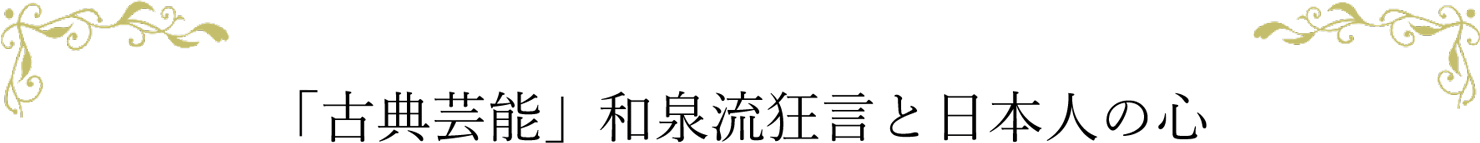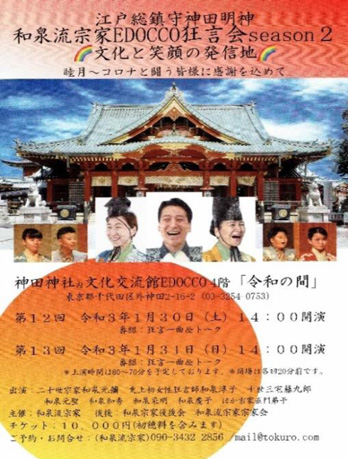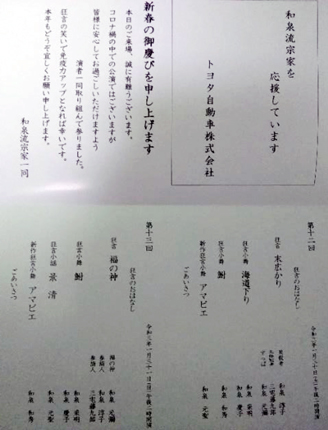河内裕二 令和3年4月1日
1.心に響かぬは歌ならず
ミュージックはあるがソングはない。
作詞家の阿久悠の言葉である。ほとんど歌詞が聞き取れない歌がミリオンセラーになる歌謡界の状況を憂えて彼はそう述べた。歌謡曲がJ-POPと呼ばれるようになった1990年代後半のことである。この言葉は、1998年に書かれたエッセイ「音楽と文楽」においては「音楽だけで文楽がない」と別の言い方がされる。「文楽」は「ぶんがく」と読み、文を楽しむという意味で、「ぶんがくと読むが文学じゃない。文楽と書くがぶんらくじゃない」とある。阿久らしい洒落た表現である。音楽を聴く人は、音は楽しんでいるが、文すなわち言葉は楽しまなくなった。彼は歌詞を軽視する世の中の風潮を嘆き続けていた。歌は言葉の存続にも関わる問題であるとし、次のように述べる。
歌に盛られた小さな言葉の一つ一つが、意外に重いことに気づいたり、思いもよらない広い世界へ導くものだということを、歌は使命として負っていたし、歌う人も聞く人もそれがあってこそ、しんみりしたり、元気づけられたり、心を開いたり、暗示を受けたりしていたのである。それは、たぶん、日常の言葉にも影響を与えていたと思う。(『昭和おもちゃ箱』120頁)
「歌は世につれ世は歌につれ」などと言われるが、歌が世相を映す鏡であるとすれば、言葉に無神経な社会になったことになる。時代や社会を言葉で表現する作詞家として阿久は誰よりもその変化を感じ取り、危機感を抱いていたのだろう。
1990年代に私は20代だった。当時、文学専攻の若者だった私が、テレビやラジオや街角で毎日耳にした流行歌こそが阿久が疑問視したミリオンセラーの歌だった。今にして思えば、人並みに流行には乗っていたが、歌に全く興味が湧かなかったのは、流れていたのが「ソング」ではなく「ミュージック」だったからだろう。心にしみなかったのだ。
あれから随分の年月が経った。最近心にしみた一曲がある。春日八郎の歌う「別れの一本杉」である。私の生まれる15年以上も前の1955年(昭和30年)に大ヒットした望郷演歌の名曲である。作詞は高野公男、作曲は船村徹。ふたりは音楽学校時代からコンビを組んで活動し、この作品でようやく成功を掴んだ。高野は翌1956年に結核のため26歳の若さで亡くなるが、船村は友の死の悲しみを乗り越えて活躍を続け、戦後歌謡界を代表する作曲家となる。船村は自伝にこう書いている。
歌は心でうたうものである。テクニックがどんなに優れていても、心のつぶやきや叫びから出たものでなければ、けっして聴く者を感動させることはできない。(『歌は心でうたうもの』2頁)
歌とは何か。阿久は「ミュージックではなくソング」だと言い、船村は「テクニックではなく心」だと言う。ふたりの考えは同じだろう。耳ではなく心に響くのが歌なのである。船村は自身の人生について「邦楽を西洋音楽より下に見る風潮や、街の片隅や黙々と生きる人々の哀感をうたう歌謡曲や演歌を蔑む傾向に対する反逆だった」と述べる。彼がその作曲家人生を歩み始めることになった出世作が「別れの一本杉」である。
2.村の外れで涙は溢れる
泣けた 泣けた
こらえきれずに泣けたっけ
あの娘と別れた哀しさに
山のかけすも鳴いていた
一本杉の石の地蔵さんのよ
村はずれ
男は生涯で三度しか泣いてはいけない。
そんな言葉を子供の頃に聞いた気がする。「人前で」という言葉が入っていたかもしれない。泣いてもよいのは、生まれた時と親が亡くなった時とあと一度。最後の一つがどうしても思い出せないが、要するに男は簡単に泣いてはいけないということだ。現在ではこの言葉も「男らしさ」「女らしさ」を前提とする発言として「ジェンダーハラスメント」と見なされるだろう。しかし転んだ子供に親が「男の子なのだから泣かない」などと言う光景は、昔は日常的によく見られた。男は泣くもんじゃない。かつては皆の共通認識だった。
「別れの一本杉」は「泣けた 泣けた」という歌詞で始まる。恋人との別れが哀しくて泣けるのだが、堪えていた涙が村外れに来ると溢れてしまう。人前では泣けないというのもあるだろう。しかし堪えきれなくなるのは、村外れでいよいよ故郷との別れになるからだ。カケスまでもが鳴く。カケスは漢字で「懸巣」と書く。木の上に枯れ枝などで巣を懸けることが名前の由来である。鳥名までもがどこか故郷を思わせる。恋人や故郷をただ離れるのではなく捨てるという気持ちだろう。男にとって三度しか泣けない残りの一回である。別れを経験しない人はいない。たとえ恋人を残して故郷を去ったことがなくても、別れの辛さや哀しさは誰もが理解し共感できる。自然に歌の世界に引き込まれてゆく。
村外れにある一本杉とその脇の地蔵。情景が目に浮かぶ。仏教では地蔵菩薩は六道すべてに現れて衆生を救うとされる。村に来る旅人や先祖を出迎え、また去る時には見送る場所になる村の境界には地蔵が立っていることが多い。作詞した高野公男は故郷の茨城の風景を思い浮かべて書いたが、歌った春日八郎の故郷の福島にも同じ風景があった。日本には同じような場所が数多く存在するだろう。一本杉と地蔵は、自分が生まれる前からそこにあり、たとえ村が変わっても、自分が死んでも、変わらずにいつまでもそこにある。泣けたのが駅のホームでは土着な感じは出ない。
船村によると、高野が付けた歌のタイトルは「泣けたっけ」だった。レコード収録が決定した際に、プロデューサーが「別れの一本杉」に変えた。歌詞も含めて「泣けた」が多すぎるからとの理由だったが、その変更は見事である。「泣けたっけ」では情景が浮かばない。「別れの一本杉」であれば、情景が浮かび郷愁を感じられるし、さらに一本杉の佇まいから孤独や寂しさも伝わってくる。
「泣けたっけ」という言葉には作詞した高野の思いが込められている。発表当時この歌の新しさは口語体の歌詞だった。さらに言えば、地方訛りのある話し言葉が使われている。高野は茨城の出身だが、「っけ」という語尾は他の方言でも使われる。地方出身者にはどこか懐かしく聞こえただろう。高野は東京で「地方」にこだわっていた。相棒の船村には「おれは茨城弁で作詞する。おまえは栃木弁でそれを曲にしろ」と言ったそうだ。彼らの作る歌が、故郷を離れて都会で暮らす人びとの心をとらえないはずがない。私も20代で愛知から上京した。
3.遠い故郷と赤い頬っぺた
遠い 遠い
想い出しても 遠い空
必ず東京へついたなら
便りおくれと云った娘
りんごの様な赤い頬っぺたのよ
あの泪
東京に出てきた理由は語られない。捨てる思いで後にして戻れないから故郷は遠い。故郷は北海道や九州でなくても茨城や栃木でもよい。遠いのは心の距離だからだ。歌の故郷はどこなのかわからない。具体化が避けられているので誰もが自分の故郷になる。三橋美智也の『リンゴ村から』(1956)のように故郷とりんごが結びつけば、生産地の東北地方か長野の話になる。「りんごの様な赤い頬っぺた」であれば、東北や長野出身者は「りんご」に、他県の出身者は「赤い頬っぺた」に気持ちが向くだろう。「空」と「りんご」の二語が出てくることで、あるいは故郷で聴いた当時は誰もが知っていたであろう「リンゴの唄」(1945)を思い出すかもしれない。
「別れの一本杉」が歌われた昭和30年代には集団就職で多くの若者が東京にやって来た。農村部の中卒者が多かった。文科省の統計では、昭和30年の高校進学率は51.5%である。中卒者は日本の高度経済成長を支える「金の卵」と呼ばれ、彼らを就職先に送り届けるために運行されたのが集団就職列車だった。昭和29年4月5日の青森発上野行きの列車が第一号と言われるが、山口覚の『集団就職とは何か』などを読むとそれ以前にもあったようだ。「別れの一本杉」の九年ほど後にヒットする井沢八郎の「あゝ上野駅」は歌詞の設定がより具体的である。就職列車で上野駅に降り立った農家出身の若者が、辛い配達の仕事をしながら啄木のように上野駅で国訛りを聞いて故郷にいる両親を思い出すのである。この時代をイメージして作られた映画に2005年公開の『ALWAYS三丁目の夕日』がある。昭和33年の東京を舞台とするこの映画では、星野六子という女性が集団就職列車で青森から下町の自動車修理工場にやって来て住み込みで働く。まだあどけなさの残る彼女は特徴的なリンゴのような赤い頬をしている。
「あゝ上野駅」や『ALWAYS三丁目の夕日』も彼らの気持ちを慮って心を動かされるが、「余白」のある「別れの一本杉」の方が心にしみる。より詩的だと言えばよいか。最後の「あの泪」という語にしても、戻れない故郷にいる恋人のなみだだから、戻るが入る「涙」ではなく「泪」なのだろう。作者の思いが込められている。
4.都会の片隅にて何を思ふや
呼んで 呼んで
そっと月夜にゃ呼んでみた
嫁にもゆかずにこの俺の
帰りひたすら待っている
あの娘はいくつ とうに二十はよ
過ぎたろに
誰でも夜は寂しい気持ちになる。夜空に浮かぶ月は人の心も照らすのか。月を見るとなぜだか故郷を思い出す。古くは唐に渡った阿部仲麻呂が帰れぬ故郷を思い「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山にいでし月かも」と詠んだ。故郷を思う時、最初に思い浮かぶのは、風景か人か思い出か。女性が浮かべば望郷演歌になる。
故郷には自分の帰りを待つ女性がいる。彼女は手紙すら来ない相手を嫁にもゆかずにひたすら待っている。東京の空に浮かぶ月を見上げなから、男はどんな気持ちになったのか。彼女の名前を叫ぶのではなく、そっと呼ぶのだ。慚愧の思いだろう。だが帰るわけにはいかない。東京でまだ何も成し遂げていない。
「とうに二十は過ぎたろ」とは何歳ぐらいを指すのだろうか。22、3歳か、あるいは20代後半までいくのだろうか。童謡「赤とんぼ」の姐やは15歳で嫁にゆくが、三木露風が作詞したのは34年も前の大正10年で姐やは奉公に来ていた女中のことだから、昭和30年代の歌の結婚年齢には参考にならない。厚生労働省の「人口動態統計」で調べてみると、昭和30年の女性の平均初婚年齢は23.8歳である。全国平均より農村部はもう少し若くなるとすると、待っている女性は結婚適齢期を越えてこのままだと結婚が難しくなる年齢だろう。結婚するのなら今直ぐにでもした方がよい。時間の余裕はない。
男は東京でどんな生活をしているのか。月を見て望郷の念がこみ上げてくるのだから、不本意でつらく厳しい生活だろう。こんな生活がいつまで続くのかと焦りや苛立ちを抱えて生きているのではないか。挫折して失意の底に沈んでいるようには思えないので、夢や希望を捨ててしまったわけではないだろう。ひたすら堪え忍ぶ日々か。
男の態度から恋人に待っていてほしいという心情は伝わってこない。どこかで自分のことは忘れて別の人を見つけてほしいと思っているのではないか。未練はあるがこれ以上待たせておくわけにもいかない。手紙を出さないのも、出せば将来を期待させるから。手紙で別れを告げることも考えただろう。しかし待ち望んだ手紙が別れの手紙だった時の彼女の悲しみは如何ばかりかと考えると書くことができない。手紙も来ない状況に実らぬ恋と諦めて自ら新たな道に歩み出してくれたなら、そう考えるのは男のずるさか優しさか。離愁に満ちた歌である。
「別れの一本杉」が発表された昭和30年は日本の高度経済成長が始まった元年である。翌31年には経済白書に「もはや戦後ではない」という有名な言葉が登場して戦後復興の終了が宣言され、高度成長は昭和48年のオイルショックまで続く。人々が豊かさや機会を求めて都会に出る。生まれ育った場所を離れた時に初めて故郷が誕生する。この時代に多くの故郷が生まれた。
望郷歌「別れの一本杉」について考える場合、都会と田舎であるとか、変わってしまった自分と変わらない故郷といった単純な二項図式で捉えるべきではない。船村が言ったように歌は心なのである。室生犀星が「ふるさとは遠きにありて思ふもの」で始まる詩で表現したように、故郷は思うものであり、思うことで故郷は生まれる。「別れの一本杉」は故郷をうたうのではない。この歌をうたう時に心の中に故郷が生まれるのである。心の中にそれぞれの一本杉が。